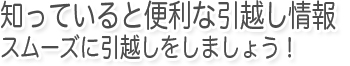お清めとして使用されるお香
香りを楽しむために利用される事が多いお香ですが、時にはお清めするために利用される事もあります。
お寺などに参拝する時や写経をする時に清めるために利用される様です。
ですので、お坊さんなどがよく使うそうです。
また、お寺の参拝に来た人にもこのお香を配ってくれるお寺もあるみたいです。
お香と言えば燃やして使用する物が多いですが、清めるために使用されるお香というのは使い方がちょっと違います。
粉末状になったお香を手にとります。そして、なじませるといい香りがします。身がひきしめられる様な感じで、すっきりとする様な香りに感じます。またどこか懐かしい様な、落ち着く様な不思議な香りですね。